今年2月から行ってきた耐震補強工事が無事完成しました。
古い2階建の木造住宅を土壁の伝統工法で補強。
京都市の補助金事業で、地域によって異なるが今回のお宅では300万円の補助金が使えました。
限界耐力計算に基づいて必要な耐力壁の配置を割りだします。
今回は土壁工法でしたが、その他にもパネルや木摺りなど別の工法でもできますが壁の配置等が若干変わってきます。どれも耐力実験を基に裏付けされた工法です。
私はよく、木造伝統工法を“こんにゃく”に、コンクリート構造を“大根”に例えます。
こんにゃくは少し手で力を加えればグニャっと曲がるが折れることはない。
大根は硬くてちょっとやそっとでは曲がらないがある一定以上の力が加わればポキッと折れる。
言い方を変えれば、前者は地震などで多少動いて傾くかもしれないが倒壊はしにくい。
後者は大きな地震で倒壊する可能性が高い。
わかりやすく表現するためで、べつにコンクリート構造を否定しているわけではありませんので。。

また、地震などでの倒れ方にも違いがあり、コンクリートの場合は砕けて崩れ落ちます。
木造の場合は、柱や梁などの木材同士が倒れそうだが、もたれ掛かるというか支えあう引っかかって支え合う状態でその真下に空間ができるので、それで人命が守られたということも過去の大きな震災時でも報告されています。
今回工事した家も同じく日本の伝統的住宅は、障子やふすまで空間を分けたり繋げたりという使い方が一般的です。つまり、壁という壁が無いので、そこに新たに耐力壁を設けて補強する部分が多かったです。その関連で、動線や日照やなども同時に計画する必要も。また、既存の木材や建具などの再利用もサブテーマでした。
耐震補強工事とは言え、そこに住む方のライフスタイルやこだわりが盛り込まれたとても価値ある工事でした。
次回ブログでは工事の詳細内容を説明しようと思います。
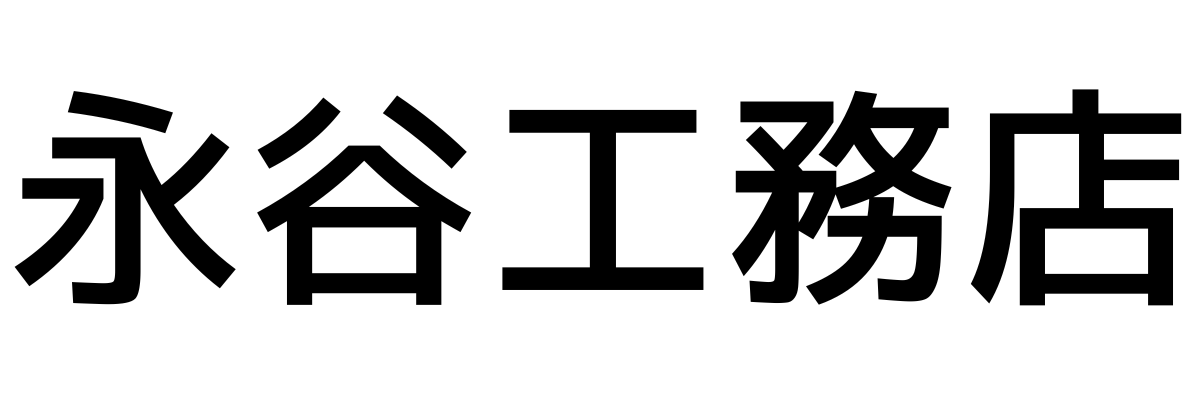

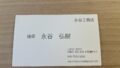

コメント